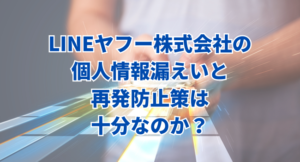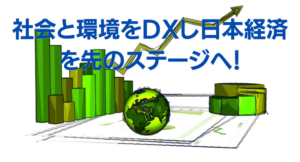経理部門は、重要な経営資源である資金をはじめ、経営に関する様々な数値を管理する部門としての役割を担っています。
そのため、経理部門のDX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)は、経理部門だけではなく、社内全体、更には取引先企業や顧客など社外のステークホルダーにまで大きな影響をもたらします。
DXportal®では、この経理のDXの重要性を踏まえて、これまでにも様々な視点から、情報を発信してまいりました。
今回は、この分野のエキスパートへのインタビューを通じて、経理のDXについての理解をより深めることを目的に、バックオフィスSaaS(Software as a Service=Webを通じて利用できる外部のソフトウェア)として大きなシェアを誇る「マネーフォワード クラウド」を開発・提供する、株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区/以下:同社)の執行役員 経理本部 本部長の松岡俊氏にお話を伺います。
同社は、企業のビジョンとして「すべての人の、『お金のプラットフォーム』になる。」を掲げており、法人だけでなく、個々人も含めてすべての人のお金の課題を解決するプラットフォームの開発・運用を行っています。いわば経理のプロフェッショナル企業です。
その「お金のプラットフォーム」をローンチする同社の中で、松岡氏は社内の経理をDXする担当者として、入社以来数多くの改革を行ってきました。
本特集では、松岡氏の豊富な経験と知見をもとに、現場で活かせる経理DXの実現のために必要な点について、システム面からマインド面まで幅広くお伺いします。
前編となる今回は、松岡氏の欧米経験を踏まえて、日本と欧米との文化の違いから感じ取られた経理DXにまつわるお話を、そして後編となる次回は、日本でDXを推進するにあたって、これからの経理のありかたや、具体的にどのようなスキルが求められるかなど、より実践的なお話を伺っていきます。
経理部門のDXに課題を抱える企業様は、どうぞご注目ください。
海外で経験したDXの取り組みと後悔
松岡氏がマネーフォワード社に入社したのは、2019年4月のことで、それ以前は、1998年から約20年間にわたってソニー株式会社の経理部で活躍していました。
2012年には英国を拠点として約5年間欧州および米国において経理業務を経験しています。
松岡氏は、これまで国内外で経理部門に関わっており、その中で経理のDXにも取り組んでいたわけですが、当時の出来事で今でも忘れられない後悔があると言います。
まずは、当時松岡氏が行っていた業務内容について、その後悔も含めて伺ってみましょう。
(松岡氏)

2009年頃、使用していた会計システムが古くなっており、システム刷新、ERP(Enterprise Resource Planning=企業内の様々な部門や業務プロセスを統合し、効率的に管理するための情報システム/以下:ERP)導入の必要に迫られていました。
その中で、ユーザー側のプロジェクトリーダーとして、変化したくない保守派と改革を進めたい改革派の調整役をしつつ、バランスを取りながらリードすることが私の役目でした。
私が特に気を付けていたことは、アドオン(標準機能だけでは実現できない要件を、個別に開発して機能追加)をいかに減らしてコストを少なくするかということです。
個々が行っている業務を部分最適化しようとすると、ソフトウェアへ新たな機能を追加するためのプログラムを開発しなければいけません。
しかし、1つひとつ要望を聞いて対応していたら、その分開発コストはかさんでしまい、膨大な予算が必要になります。
ただ変化を怖れて現状維持をするためのアドオンなのか、自社の独自競争力につながるアドオンなのかを適切に判断し、現場の方々と丁寧に向き合うことが大規模ERP導入などDX推進を成功させるためには重要だと感じています。
今でも後悔している失敗談として、とあるコンサルタントからERP標準機能にはないが、「ほとんどの日系企業は仕訳承認用にハンコを押すための紙を出力するアドオンを開発しているので、アドオンすべき」というアドバイスをもらいました。
私の中では、紙による業務はなるべく避けたいと考えていましたが、当時はペーパーレスでの業務経験が無かったこともあり、紙処理を行うシステムを要件として組み込んでしまったのです。
1度システムに組み込んでしまうと、しばらくはそのシステムを使い続けないといけないため、その後の長い期間、生産性に大きな影響を与えてしまったと反省しています。
ただ、当時の失敗経験が現在のDXに活かされているのだと思います。
欧米で経験したペーパーレス経理業務
日本は長きにわたる独特のハンコ文化の影響もあり、ペーパーレス化が進まず、他の先進諸国と比較してDX後進国と言われています。
松岡氏によると、欧米の経理業務では以前からペーパーレスが進んでいたとのことで、同氏は未だに紙文化が根強く残る日本について危機感を覚えていると言います。
欧米と日本、両方のDX推進を経験したからこそ感じた、日本のDX推進状況についてお伺いしました。
(松岡氏)

英国に赴任した2012年の当時から、欧米ではペーパーレス化が進んでいる状況でした。
日本では紙での手続きが当たり前のように行われている中、既に10年以上も前から、欧米諸国ではペーパーレスでの作業が行われていたのです。
紙とデジタルでのやり取りでは、作業効率や生産性に大きな差が出てしまいます。
目まぐるしく変化しているグローバルなビジネスに対応するには、今後はより経理のDXが必要になるでしょう。
ペーパーレスの経理では承認のために紙をとりまわす時間、書類を探す時間、書類を保存するための作業が大幅に削減され、より本質的な分析や検討により多くの時間を使えると業務の中で感じています。
また、これからの時代は自社だけで全ての経理業務を対応するのではなく、ノンコア業務など外部に任せられる業務はBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング/業務プロセスの一部を専門業者に外部委託すること)を活用するなど、人材不足の課題に対応する施策を検討する必要があります。
欧米では経理ペーパーレスおよび業務標準化により、国をまたがった形でのBPOが実現しています。
デジタル化し、クラウドなど共通のデータサーバーに保管しておけば、物理的に郵送をする必要がないので、国をまたがった協業が可能となります。
もちろん、日本語という言語の壁もあるのですが、まずはデジタル化の壁を越えることが重要とだと感じました。
いつまでも紙とハンコによる業務を行っていると、欧米との生産性の差が広がるばかりです。
まだ対応されていない企業は少しずつで良いので、できるところからデジタル化に取り組まれると良いと思います。
日本の経理DXを妨げる3つの要因
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表した「日米比較調査にみるDXの戦略、人材、技術」によると、「DXに取り組んでいるか」の問いに対して、全社的、あるいは一部の部門ごとに少しでも「取り組んでいる」と答えた企業の割合は、日本では55.8%の企業に留まっています。
それに対して、米国では79.2%もの企業が既にDXに取り組んでいるという結果が出ており、日本とは大きな差があることがわかります。
では、実際に欧米と日本で経理のプロセス改善を進めた松岡氏が、それぞれの場所でDX推進に取り組む中で感じた、DXを妨げる要因とはどのようなものだったのでしょうか。
変化を恐れる
(松岡氏)

経理部門は会社を管理する役割として、企業内でも「守りの部門」にあたり、そのためそこで働く人々の思考も保守的になりがちなのではないでしょうか。
そのためか、経理部門で働く人の多くは、変化を恐れる傾向にあります。
これは欧米でも同様で、むしろ欧米のほうが変革の結果、自身の仕事がなくなるのではという不安から、より抵抗が強い印象を受けました。
日本においては自身の仕事がどうなるのかという不安に加えて、紙とハンコへの信頼性が厚く、ペーパーレスの経理プロセスで本当に仕事が回るのか不安に思う結果、抵抗を持つ人が多い印象です。
このような変化を打開するためには、変革後の各自の仕事内容がどうなるのかを伝える、丁寧なコミュニケーションが重要になります。
また、ペーパーレスで本当に仕事が回るのかという不安に対しては、「他社成功事例」を示すことで、納得してもらいやすくなります。
他社の具体的な成功事例を示して、会社全体や個人に対してどのようなメリットがあるのかを提示することで、よりDXを推進しやすくなるでしょう。
自社でゼロから要件を検討して開発するソフトよりは、同じ業種・規模での成功事例が多いクラウドサービスの適用から、まずは検討すると良いかもしれません。
改善範囲を極小化してしまう
(松岡氏)

DXは一部分だけ最適化するなど、狭い範囲だけで考えるのではなく、会社全体のプロセスを見据えたうえでの取り組みが必要です。
ところが、摩擦・反発に対する恐れや、相手へ配慮「し過ぎて」しまい改善範囲を自部門内だけで留めてしまう場合があります。
経理をDXするためには経理以外の部門も巻き込み、そもそものプロセスから変えていかないと、抜本的なプロセス変革につなげることは難しいでしょう。
実際に当社で請求書処理業務のDXを進める際、経理内部からは「現場部署のプロセスは一切変えずに引き続き紙とハンコで進め、経理内部プロセスのみ電子化しよう」という案がでてきたことがあります。
しかし、事前調査の結果、請求書処理における課題は、現場部署のプロセスから変革していかないと解消できないことが分かっていました。
そのため、DXを推進させるにあたり、「請求書処理をデジタル化することで経理部以外の現場にもどのようなメリットがあるか」ということを丁寧に説明し、現場部署を巻き込んで、現場の段階からデジタル化をする改善を実施し、結果的にプロセス全般の改善を実現することができたのです。
もし、独自の判断で改善範囲を極小化してしまっていたら、生産性向上やデータ活用の範囲などが限定的になってしまい、求めていたDXにはならなくなってしまっていたでしょう。
DXを推進するリーダーとして重要なことは、どのようなゴールを目指しているのかをできる限り具体的な「絵」としてメンバーと共有することです。
これができれば、視野を広くしながらDXに取り組めると考えています。
システム導入で力尽きてしまう
(松岡氏)

システム導入までに多くの労力、時間を使い、そこで力尽きてしまった結果、DX本来のメリットを受けられないケースも起きていると思います。
これは、特に大規模なオンプレミス(企業や組織が自社の物理的な施設内にコンピューター、サーバー、データストレージ、ネットワーク機器などのITリソースを設置・管理・運用すること)のシステムについて、要件定義からスタートするようなプロジェクトで起きがちです。
経済産業省の「2025年の崖」レポートにもあるように、社会の変化に対応しつづける企業文化を醸成することがDXの本質と考えると、システムの導入はゴールではなく、導入後の改善を継続することが本質なのではないでしょうか。
システムの導入は可能な限り、クラウドにプロセスを合わせる形で短期間で終え、そこで力尽きることなく導入後にリリースされる新機能を活用し、社会の変化に対応する形で改善を継続することが重要です。