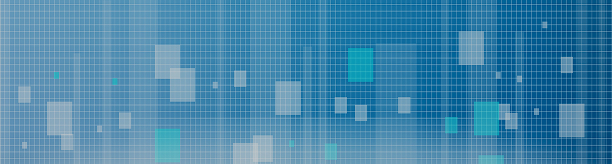- share :
企業のDX(デジタルトランスフォーメーション/以下:DX)を推進する上で、近年よく聞かれる言葉でもある「オープンイノベーション」。
DXを推進し、新たな企業価値を生み出す上では非常に有効な考え方ですが、果たしてどれだけの企業がその意味を正確に理解しているでしょうか。
この記事では、「真のオープンイノベーション」について考えます。
- これからDXを推進していきたい
- 自社のDX推進に行き詰まりを感じている
このような企業の経営者・担当者の方は、どうぞ最後まで読んで自社のDXを考え直す一助としてください。
オープンイノベーションとクローズドイノベーション
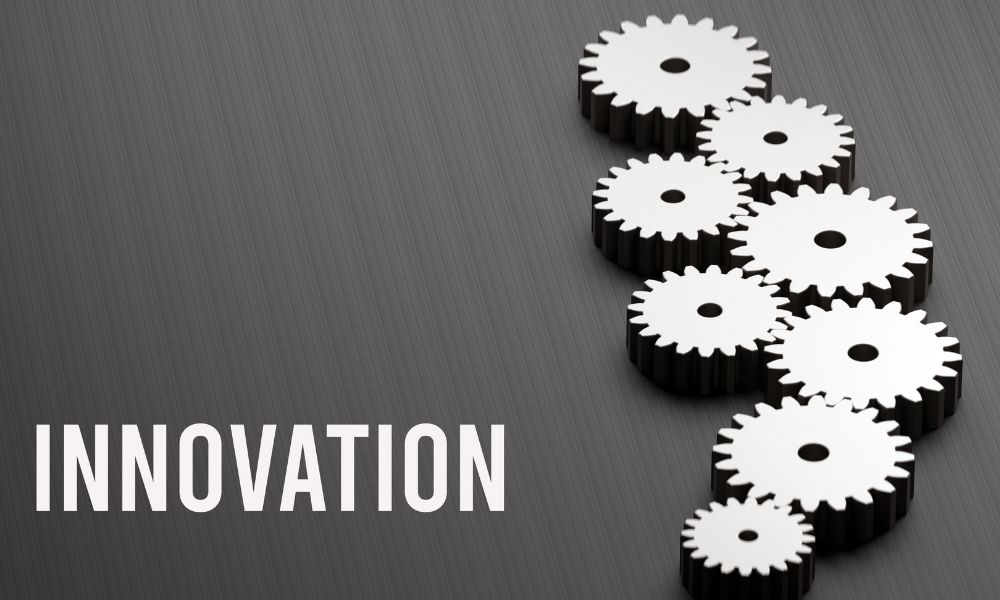
新型コロナウイルスが蔓延する世の中となり、企業のDX推進の波はますます加速してきました。
その流れの中、自社のみで行うDX推進に限界を感じ、外部企業や組織との連携を考える企業も多いのではないでしょうか。
そこで考えたいのがオープンイノベーションというビジネスモデルです。
オープンイノベーションとは、2003年にハーバード大学経営大学院のヘンリー・チェスブロウ教授(当時)によって提唱された概念で、「組織内部のイノベーションを促進するために、企業の内部と外部との技術やアイデアの流動性を高め、組織内で創出されたイノベーションをさらに組織外に展開するイノベーションモデル」と定義されています。
IT技術を用いて、企業の新しいビジネスモデルを創出することを目的としたDX推進を成功へ導くためにも重要な鍵となっています。
オープンイノベーションに対し、自社の組織のみで開発を行い、新たなイノベーションを創出することを「クローズドイノベーション」と呼び、社内外の境目があるかないかが両者の違いです。
諸外国に遅れをとる日本のオープンイノベーション

日本企業の多くは古くからクローズドイノベーションの考え方が主流で、競業他社よりもすぐれた技術開発を目指し、その技術の独占することも目的としていました。
これは技術の流出を防止できることに加え、自社のみで完結するスタイルのため、イノベーションに成功した際に享受できる利益も多いというメリットがありました。それによって、唯一無二の技術力を持つ日本企業が発展してきたのも事実です。
しかし、クローズドイノベーションは、自社のみで開発に莫大な投資や時間をかけなければならず、IT技術の導入により開発スピードがますます加速する時代の流れには対応しにくいことが大きな問題となってきました。
海外のトップ企業などは、このようなクローズドイノベーションの限界にいち早く気が付き、こぞってオープンイノベーションの概念を取り入れた経営方針へとシフトしています。
一方、日本ではまだまだオープンイノベーションへとシフトする企業は少数で、諸外国に大きく遅れを取っているのが現状です。
しかし、人口減少や就労人員の高齢化、日本の国内市場の縮小化に伴う開発予算の減少、アジア諸国を中心とした新興国の技術発展の高まりなど、クローズドイノベーションだけでは戦い切れない時代が既に始まっています。
オープンイノベーション導入のメリット

DX推進においても、諸外国と比べて大きな遅れを取っていると言われる日本企業。
これは「DX」に対する企業の理解度が足りないということが最大の問題点ですが、オープンイノベーションに関しても企業の意識改革が必要なのは言うまでもありません。
クローズドイノベーションに固執する日本企業の経営陣の意識を払拭するためにも、ここでオープンイノベーション導入によるメリットを考えてみます。
外部組織の知識や技術を共有できる

クローズドイノベーションでは、新しい技術や商品・サービスといったものを創り出すためには、研究開発などを自社でイチから進めていかなければなりませんでした。
しかし、オープンイノベーションで外部の知見を獲得するということは、自社の視点だけでなく、より多角的な視点を得られるということでもありますので、さまざまな新しい技術やサービス、あるいはノウハウの獲得にも繋がります。
特に、同業種の企業だけでなく、異業種の企業や組織と連携することにより、それまででは考えられなかった、より新たな将来の成長へ向けたステップとなる可能性も含んでいるのです。
DX推進速度のスピードアップ

外部の技術開発スキルやマーケティング手法など、自社では扱ってこなかったリソースを取り入れることにより、より幅広い戦略を取ることができます。
幅広い戦略を取ることができるということは、そのままPDCAサイクルをスモールステップで回すことを可能とし、開発スピードがアップすることに繋がるのは間違いありません。
特に異業種・異分野の知見を取り入れることにより、自社のみの開発では到底得られないデータの蓄積も可能ですので、客観的な視点を取り入れたDX推進の大幅なスピードアップが期待できます。
短期間・低コストでの開発が可能

自社でイチから開発ステップを踏んだ場合、製品やサービスのリリースまでには膨大な時間と資金を投入する必要があります。
しかし、外部との連携を取ることにより、人的・物的リソースが掛け算となり、より短期間での開発も可能となります。
さらに、すべてのコストを自社で負担する必要がなくなるために、大幅なコストダウンを実現することができます。
オープンイノベーション導入の問題点

DX推進において、欠くことのできないオープンイノベーションという考え方ですが、企業がその概念を取り入れるためには、まだまだ解決すべき課題はあります。
目的を明確にする

既存の業務をIT技術によって革新し、新たな企業価値を創出することを目指すDXにおいては、ただ闇雲にIT導入するだけでは場当たり的な効率化しかできず、真の意味で企業の新しい価値を生み出すまでには至りません。
これはオープンイノベーションの場合も同様です。「新しい視点を自社に取り入れるために異業種とコラボすればいい」といったレベルの考え方では、真のオープンイノベーションとは言えないでしょう。
プロジェクトの目的や理念を見失い、漠然とした受動的な動きで目先の利益に振り回されていては、オープンイノベーションの真の価値は得られません。
相互利益を目指す

仮に、企業規模が対等と言えない企業・組織同士の場合でも、そこに上下関係が発生してしまっては、オープンイノベーションの大きな妨げとなります。
利益が一方から一方へ流れる受発注という関係ではなく、コラボする企業・組織が互いに利益を享受できる関係性となっておらず、どちらか(受注側)がリスクを負うような日本の悪しき商習慣の中では、真のオープンイノベーションは生まれにくいものです。
あくまでも対等な立場の「パートナー」であると認識し、上下関係でない敬意を持った関係を構築することが必要なのです。
自社の技術流出への懸念

これまでのクローズドイノベーションに慣れている日本企業では、いきなり開かれた社外とのリソース交換を求められても、自社の財産である「技術の流出」を懸念するでしょう。
特に、大企業と独自のアイデアや技術を持つスタートアップ企業が連携する場合、「技術の流出」に対するリスク管理は大きな問題です。
独自のアイデアを持つスタートアップ企業がそのアイデアや技術を提供する代わりに、大企業側も相応の投資を行うなど、リスクを分担する契約とすることが必要で、その契約内容もその都度チェックを行い、必要があれば互いに変更対応する柔軟な企業体制を作り上げる必要もあります。
まとめ
現代のDXを語る上で欠かせないキーワードでもある「オープンイノベーション」。
日本企業が今後も国際社会で戦い続けるためには、「日本国内のみならず海外を含めたパートナーとの価値ある連携」は必要な施策となります。
コロナ禍でますます加速する企業のあり方の変化や、社会のあらゆる変化に対応するためにも、本当の意味でのオープンイノベーションの意味を理解し、自社の成長のために取り入れていく姿勢が、これからの日本企業にも求められる時代になっているのではないでしょうか。

執筆者
株式会社MU 代表取締役社長
山田 元樹
社名である「MU」の由来は、「Minority(少数)」+「United(団結)」という意味。企業のDX推進・支援を過去のエンジニア経験を活かし、エンジニア + 経営視点で行う。DX推進の観点も含め上場企業をはじめ多数実績を持つ。