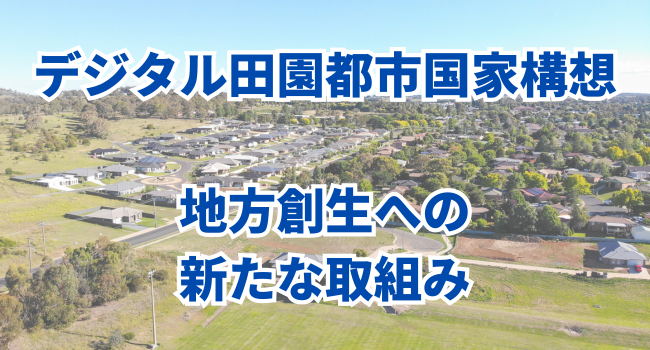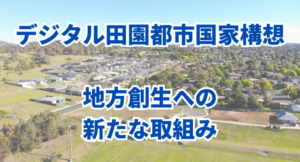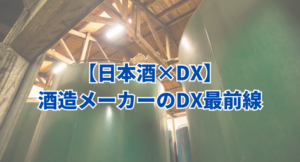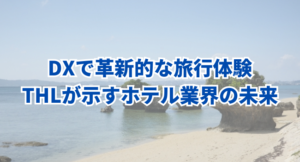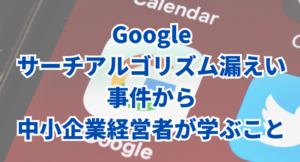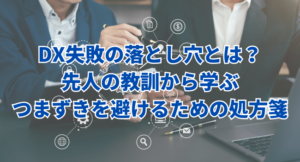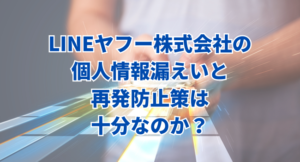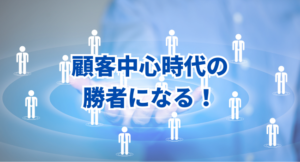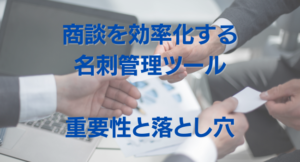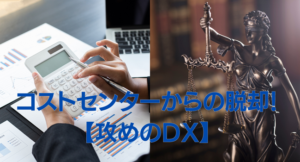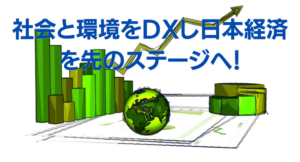デジタル田園都市国家構想の課題と今後の展望

デジタル田園都市国家構想は、日本全体の地方創生を目指す画期的な取り組みですが、その成功のためには多くの課題を克服する必要があります。特にデジタル技術の普及に伴うデジタルリテラシーの格差や、セキュリティ・プライバシー保護への対策は重要です。
また、インフラ整備にかかるコスト負担や地域社会の持続的な参加も課題として指摘されています。本章では、構想が直面する具体的な課題と、その解決に向けた今後の展望を詳しく見ていきます。
課題の整理
デジタル田園都市国家構想の成功には、いくつかの重要な課題が存在します。まず、地方では高齢者を中心にデジタルリテラシーの低さが問題となっており、技術を適切に使いこなすための支援が不可欠です。
リモート診療や行政手続きのオンライン化を進めたとしても、スマホやPCの操作に不慣れな高齢者への支援が十分でなければ、かえって利便性を阻む要因になりかねません。これを解決するには、地方行政と企業が協力した、IT教育やサポート体制の整備が急務でしょう。
また、デジタル基盤の整備には導入コストの負担が自治体に重くのしかかる問題もあります。5G通信網やデータセンターの構築、IoT設備の導入は、特に小規模な地方自治体にとって大きな財政負担となり得るでしょう。
これを解決するためにも、国や民間企業との官民連携が欠かせません。
さらに、デジタル社会における個人情報の保護とセキュリティ対策も課題です。医療データや農業の生産情報などがデジタル化される中で、サイバー攻撃への対応とプライバシー保護の強化が求められます。
これらの課題を解決しなければ、住民の信頼を得ることが難しく、構想の効果が十分に発揮されない可能性すらあるのです。
今後の展望
今後、デジタル田園都市国家構想を成功に導くためには、単なる技術導入にとどまらず、地域が主体的に取り組む仕組みを整えることが重要な鍵となるはずです。
地方自治体、企業、そして住民が一体となり、地域のニーズに合わせた柔軟な取り組みを進めることで、持続可能な社会の実現が可能となります。
例えば、地元の特産品をスマート農業で生産し、それをECプラットフォームで全国に販売するような形をとれば、地域経済の強みを生かすことができるでしょう。
また、今後の展望としては「共創型スマートシティ」のような、自治体と住民が共にデジタル基盤を整えるプロジェクトが鍵となるでしょう。
そのためには、住民からのアイディアを募集したり、ワークショップを通じて、人々のニーズを踏まえた政策の実行が期待されます。
国は地方自治体の自主性を尊重しながら、各地域に適した支援プログラムを提供しなければなりません。
また、5Gインフラの整備を一層加速させ、遠隔医療やスマート農業をはじめとしたデジタルサービスが地方でも当たり前になる社会を目指す必要があります。これにより、都市への人口集中を緩和し、地方への定住の魅力を高めることが可能となるでしょう。
地域のニーズに応じたプロジェクトが展開され、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルの創出が期待されると同時に、持続可能な発展を実現するため、環境負荷の軽減や資源の有効活用も重視されています。
まとめ~地方創生とデジタル社会の共存
デジタル田園都市国家構想は、日本全体のバランスの取れた発展を促進する重要な取り組みです。
この構想は、地方と都市の格差を是正するだけでなく、地方社会の持続可能な成長を目指し、経済、社会、環境の三位一体での発展を重視しています。
この構想の成功には、地方自治体、企業、地域住民の協力が欠かせません。特に、地方自治体が主体的に地域の課題を解決する力を持ち、地域住民の参加を促進する仕組みが重要です。
また、企業との協働により、デジタル技術を活用した新しい産業を育て、地域に新たな雇用を生み出すことも必要でしょう。
今後、こうした多様なステークホルダーの協力を促しながら、地域独自の魅力を最大化することで、デジタル社会と地方社会の共存は実現するのです。
政府がこの構想を通じて、地方の暮らしをさらに魅力的で活力あるものにし、日本全体の持続可能な発展につなげることができるのか。国の対応が期待されると同時に、我々一人ひとりが自分事として考えていくことこそが、よりよい未来を拓いていく鍵となっていくはずです。