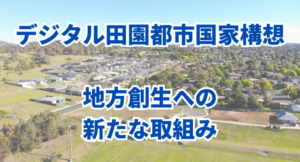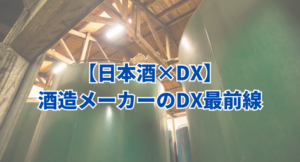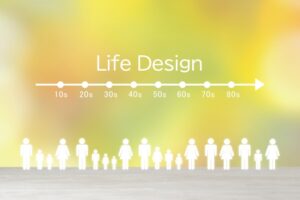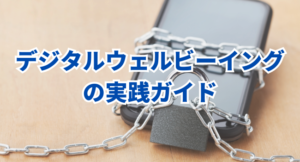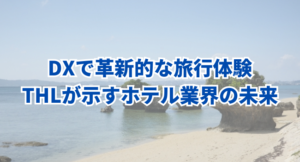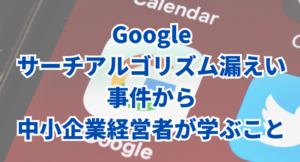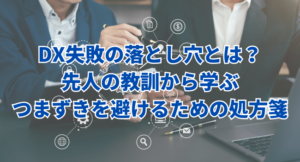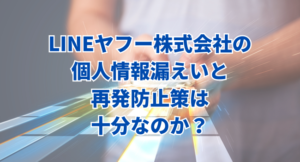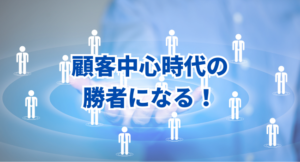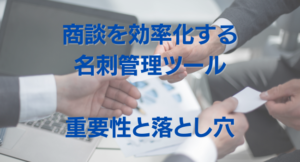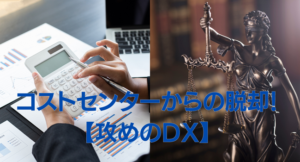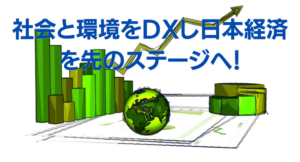デジタルリテラシーを習得する効果

ビジネスパーソン1人ひとり、あるいは組織としてデジタルリテラシーを習得することにより、次のような効果が得られます。
社会や組織のデジタル変化を自分事として捉えられるようになる

生活のあらゆる場面でDXの推進が求められているため、企業や学校など所属している組織においても、多かれ少なかれデジタルによる変化が訪れています。
社会のデジタル化は、まさに身の回りで起きている変化なのです。
その変化を正しく理解し、適切に対応していくことができなければ、これから先の未来でビジネスパーソンとして生き残っていくことは難しいと言わざるを得ません。
社会や組織のデジタル変化を自分事として捉え、前向きに取り組むために、まずは個々人がデジタルリテラシーを持つことが求められるのです。
ある組織に所属するすべてのビジネスパーソンがデジタルリテラシーを習得することができれば、その組織のDXは加速度的に進んでいきます。
こうした流れは、単にその組織のDXを進めるだけでなく、周囲のデジタルへの取り組みを前向きに応援する環境が作れるため、日本社会全体のDXを手助けしていくこともできるでしょう。
つまり、デジタルリテラシーを持った組織が増えていけば、回り回って人々が暮らしやすい、よりよい社会の実現が進んでいくのです。
「わからないから怖い」というのは誰しもが抱く感情です。
デジタルに対する不理解や知識不足から来る漠然とした不安を、デジタルリテラシーを身に着けることで払拭していけば、この変化を社会全体で前向きなものとして受け止められるように変わっていくはずです。
デジタル活用の企画立案に参画できる

すべてのビジネスパーソンがデジタルリテラシーを習得できれば、単に周囲のプロジェクトを応援するという環境構築だけでなく、それぞれが自分の身の回りを改善するためのデジタル活用のアイデアが生まれる土壌が作られるでしょう。
デジタルの活用とは、どの組織にも当てはまる最適解があるわけではありません。
多様化した環境や組織の状況によって有効なデジタル活用の方法は異なるため、それぞれに適した利活用の方法を柔軟に模索しなければなりません。
1人ひとりがデジタルリテラシーを身に着けた上で、効果的なデジタル活用について検討してはじめて、真に効果のある活用方法が見つかるのです。
例えば、デジタルリテラシーを持たない人が、今の業務をデジタルによって改善しようとしても、デジタル活用のアイディアが生まれるわけはありません。
この状態では、ただ現状の不満を列挙するだけにしかならず、せいぜい課題を整理して「デジタルを作る人」に伝えるだけになってしまうでしょう。
そもそも現状の課題が「デジタルを活用できていないこと」に起因している場合、いくら新しいデジタルツールを開発しても使いこなすことができないので、この方法では一向に改善策は生まれないのです。
しかし、個々人がデジタルリテラシーを習得していれば、自分たちだけでソリューションの開発までは行えなくとも、デジタルによってどのような手順を踏めば開発への道筋が見つけられるかがわかるでしょう。
この段階で、現状の課題を分析し、解決策を模索していけば、漠然とした不満ではなく、より具体的なイメージをもったアイデアを生み出していけるはずです。
こうして生まれたアイデアは巡り巡って、今よりもっと積極的なデジタルの利活用に繋がり、DX推進にもとづく新しい価値の創出へ至る近道を示すことにもなるでしょう。
デジタルを使う人から作る人へのステップになる
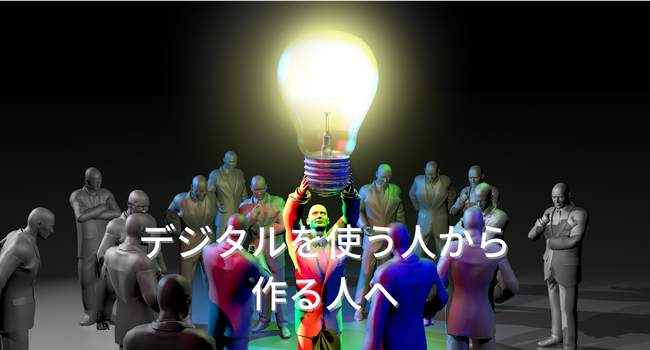
すべてのビジネスパーソンに求められているデジタルリテラシーとは、デジタルを作り開発する能力ではなく、デジタルを適切に使う能力だということは先述の通りです。
しかし、デジタルリテラシーを習得した人の中には、デジタルに興味を持ち、自ら開発したいと考える人材も生まれてくるでしょう。
こうした意欲を持った人材の誕生は、一部のIT企業に限った話ではなく、すべての企業にとって幸運なことです。
もちろん、日本企業のすべての人材がデジタルを作ることのできる人材になる必要はありません。
とはいえ、デジタルリテラシーの習得をきっかけにデジタルにもっと興味を持つ人材が増えていけば、業務へのデジタル導入をよりスムーズに、より積極的に進められるようになるでしょう。
また、こうした人材のスキルアップを支援していくことができれば、組織のDX内製化も進みます。
繰り返しにはなりますが、日本のDX推進が世界に遅れを取っている一番大きな課題は、DX人材の不足です。
デジタルを使える人材の不足によるデジタルツール導入の遅れは、結果的にデジタルに関心を持つ人材が増加しない原因にもなっています。
その結果、デジタルツールの開発を含めたDX推進においては、なかなか芳しい成果が出ないのです。
しかし、すべてのビジネスパーソンへのデジタルリテラシー習得を推し進めることで、そうした問題も解決に進むかもしれません。
デジタルリテラシーを習得した人材の中から、単に導入されたデジタルを過不足なく利用するだけでなく、やがてはデジタルエンジニアや企画者など、様々な役割を持つ人材が生まれてくれば、「デジタルを作る」側の人材も増加してくると期待できるからです。
世界的なツールの開発にまで至らなくとも、企業においてもそうした人材が増え、組織化することができれば、デジタルを活用した新たな価値の創出に繋がっていくでしょう。
経済産業省のデジタル育成プラットフォームポータルサイト「マナビDX」

デジタル化が加速する現代において、デジタル人材の育成は日本のDX推進における重要な課題です。経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)はこの課題解決に向けて、デジタル人材育成のためのプラットフォームポータルサイト「マナビDX」を開設しました。
この章では、デジタルスキル向上を目指すビジネスパーソンに向けて、「マナビDX」の特徴や活用方法、おすすめの講座などを詳しく解説していきます。
マナビDXとは
「マナビDX」は、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)が運営するデジタル人材育成プラットフォームです。日本全体のデジタルスキル向上を目指し、個人や企業がDXの基礎から実践まで幅広く学べるリソースを提供しています。
特に、デジタル初心者から専門家まで、それぞれのレベルに応じた講座や教材が揃っており、独学でスキルを磨きたいビジネスパーソンにも最適です。
ビジネス現場で即役立つ内容から、長期的なキャリア形成を見据えた深い知識まで、デジタルスキル標準などのスキル標準への対応を経産省とIPAが審査し、合格した講座のみを掲載しています。
おすすめ講座
- DXリテラシー基礎講座:IT/デジタルに不慣れな方向けに、DXの本質をわかりやすく解説し、全社員のDXリテラシー底上げを目指す
- 初心者のためのデータ分析法入門:統計学やデータ分析の基礎を、事例を用いてわかりやすく解説(PC操作は不要)
- ChatGPTの基本的な使い方を学ぼう:ChatGPT初心者向けに、効果的なプロンプト作成方法や活用事例を学び、実践的なスキル習得を目指す
- データスペース入門:データ主権の考え方、データスペースの内容、メリット、デジタル基盤について学び、デジタル化社会への理解を深める
登録方法と学習環境
「マナビDX」の講座は、多くの場合無料で受講可能です。公式WEBサイトでアカウントを作成し、自分の興味やスキルレベルに応じた講座を選択するだけで始められます。
学習はオンラインで完結するため、時間や場所を問わず取り組むことができます。
ビジネスパーソンに向けた活用の提案
「マナビDX」を活用することで、個々のスキルアップにとどまらず、組織全体でのデジタルリテラシー向上が期待できます。上記で紹介した講座を通じて、日々の業務改善や新しいプロジェクトの推進に直結する知識を習得し、DXをさらに加速させてください。
まとめ:産業界全体でデジタル人材育成の加速を目指す
この記事では、すべてのビジネスパーソンが身につけるべきデジタルリテラシーに関して、デジタルリテラシー協議会が推し進める「Di-Lite」について解説し、その習得効果を具体的に示しました。
さらに、デジタルリテラシー習得を支援する「DX推進パスポート」や経済産業省のデジタル人材育成プラットフォーム「マナビDX」といった最新の取り組みも紹介しました。
デジタル技術は常に進化し続けています。組織が変化に柔軟に対応し、DXを推進していくためには、一部の専門家だけでなく、すべてのビジネスパーソンがデジタルリテラシーを身につける必要があります。
「Di-Lite」が掲げる『全員に、全体を。』というキャッチフレーズの通り、デジタル人材とは、まさに「あなた」のことなのです。
デジタルリテラシーを習得し、変化の激しい現代社会に対応できるデジタル人材を目指すと同時に、企業や組織全体でDX推進に取り組み、より良い社会を創造していくために、共に前進していきましょう。